水生植物とは、河川や湖沼、池などの水中や水辺に生育し、植物体のすべて、あるいは一部を水に浸けている植物の総称です。水生植物は形態と機能から浮標(浮遊)植物、沈水植物、浮葉植物、抽水(挺水)植物の4種類に分類されます。
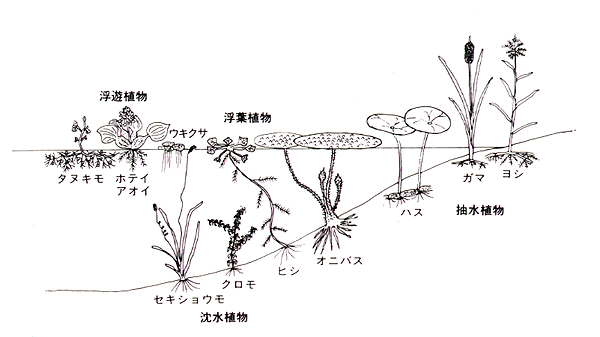
水性植物を育てるうえで大切なのは、上図に示すとおり各種類に適した水位です。夏期など水温が高くなり蒸発する恐れがある場合は注意が必要です。ほとんどの水生植物は肥料を必要としません。過剰な肥料分は富栄養化となり、アオコやアオミドロ発生の原因となります。水生植物を固定させるためにビオトープの底に荒木田(田んぼの土)を敷くケースを見かけますが、アクアフォレストが一番最初にビオトープを試作した時にこれを行い、アオコやアオミドロが大発生して大変な思いをしたことがあります。水生植物を固定するのは土ではなく、石などを使用することをお勧めします。
水生植物を植栽することで、窒素やリンの吸収、植物体表面に付着した微生物による有機物の分解が期待できます。特に抽水植物は、水質の浄化に役立つとともに魚類や鳥類の繁殖・成育の場にもなります。水質浄化には、栄養分を吸収して繁茂した水性植物を適度に刈り取ることも必要です。
参考:水生植物の販売浅見園のホームページ




